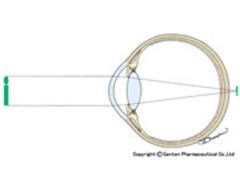眼科のご案内
診療内容
眼は小さいながらも複雑かつ精巧なシステムを持つ器官であり、扱う疾患も多岐に渡ります。当院では、
白内障、緑内障、網膜剥離、黄斑円孔、黄斑上膜、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、ぶどう膜炎、角結膜疾患、
難治性アレルギー性結膜炎、小児の斜視弱視、眼形成などの幅広い眼疾患に対応しております。
患者さんに対しては、最良の眼科医療を提供し、一人ひとりに満足していただけるように、
スタッフ一同日々努力しております。
当院で最も多く行っている白内障手術に関しては、最新の超音波白内障手術装置を使用し、
入院治療で対応しております。また、ご希望の方には、
多焦点眼内レンズを用いた選定療養手術(一部自費)の手術も可能です。循環器疾患、
糖尿病などの全身疾患がある場合には、専門の診療科と連携し、
全身管理を十分に行って手術を受けていただきます。
当院で特に力を入れているのが、網膜・硝子体疾患に対する治療です。薬物治療(ステロイド、
抗VEGFなど)やレーザー治療はもちろん、最新システム等を用いた硝子体手術も行っております。
また網膜剥離、外傷など緊急性を要する手術に関しても、柔軟に対応しています。
緑内障に関しては、濾過手術をはじめ、近年注目を集めているMIGS(低侵襲緑内障手術)
やアーメド緑内障バルブを用いた緑内障チューブシャント手術など幅広く対応が可能です。
また、小児の斜視弱視に関しては専門外来を開設、眼瞼下垂、
内反症をはじめとする眼瞼疾患への眼形成手術も可能です。
眼科疾患でお困りのことがありましたら、御紹介いただければ幸いです。
当院での加療例
硝子体手術
・網膜剥離
網膜剥離は、眼球内部の網膜が剥がれ落ちてしまう病気です。網膜が剥がれることで視力低下や視野狭窄、
飛蚊症などの症状が現れます。発症の原因は様々ですが、外傷・加齢・強度の近視などがリスクになります。
治療が遅れると視力が十分回復しないこともあるため、診断後は速やかに手術を施行します。
・網膜前膜(ERM)
物を見るのに最も重要な場所を黄斑と呼びます。
加齢などに伴いこの黄斑に膜が張ることによって物が歪んで見えたり、大きく見えたりすることがあります。
放置により症状が進行した場合強い後遺症が残る場合があります。
手術では網膜前膜を除去し、再発生予防のため内境界膜という網膜の表面の膜の剥離除去も行います。
・黄斑円孔
物を見るのに最も重要な場所、黄斑に穴が開いてしまう病気です。
穴があいてしまうのは目の中のゼリー状の成分(硝子体)の牽引が原因と言われています。
内境界膜という網膜の表面の膜の剥離除去を行い、眼の中に膨張性のガスを注入します。
術後は円孔の大きさにより、数日~10日程度のうつ伏せ姿勢が必要です。
緑内障手術
・濾過手術(Express、Trabeclectomy)
緑内障の進行を抑えるには眼圧を下げる必要があります。
点眼で進行を抑えるのが困難な方は手術により眼圧を下げる必要があります。
濾過手術は前房内から結膜下にバイパスを作成し、眼の中の水を逃がすことで眼圧を下げます。
入院期間は経過により1-2週間となります。
・流出路再建術(トラベクトロトミー)
緑内障の手術の中では低侵襲緑内障手術(MIGS)と呼ばれる負担の少ない手術です。
手術には通常リスクを伴いますが、
このような侵襲の少ない治療選択肢の登場によって早期緑内障への手術加療も可能となりました。
本来の房水の流れにおける排水口の蓋の役割を果たす線維柱帯と呼ばれる部分を切り開くことによって、
水の流れを改善し眼圧を下げます。排水口の先は静脈につながっているため、
切開することによりしばらくの間は出血で見えにくくなります。ほとんどは数日で回復します。
・iStent inject W
流出路再建術と同様、MIGSと呼ばれる緑内障手術で、白内障手術に併用して施行する最新の手術です。
房水の出口である線維柱帯に微小なインプラントを挿入することで、眼圧を下げる手術です。
前述の流出路再建術と比較して、術後の出血が少なく、術後早期から視力改善が得られます。
・インプラント挿入術(アーメド緑内障バルブ)
インプラントによる緑内障治療は、
血管新生緑内障などの難治性緑内障や複数回の手術で眼圧管理のできなかった方に対する治療法です。
複数あるインプラントの中でもアーメド緑内障バルブは調圧弁による眼圧調整を行うため術後合併症も少ないインプラントです。
一般的には前房内に挿入しますが、内皮の少ない症例では毛様溝、
硝子体手術を併用する場合は硝子体腔に挿入するなど症例によって使い分けが可能です。
抗VEGF療法
加齢黄斑変性や網膜静脈閉塞症、糖尿病網膜症などの網膜の疾患により、黄斑に浮腫が生じると、
ゆがみや中心暗点、視力低下などの症状が出現します。
これらの疾患では、体内のVEGFという物質が、
新生血管の増殖や黄斑浮腫の悪化に関与していることがわかっています。
抗VEGF治療はこのVEGFの働きを抑える薬剤を眼内に注射することにより、黄斑浮腫を改善させ、
病気の進行を抑制する治療法です。当院では全身状態や黄斑の浮腫の形状から、
国内で使用できる幅広い薬剤をそろえて疾患に応じた対応をしております。
【2024年度手術実績】
| 表示名称 | 件数 | 表示名称 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 水晶体再建術 | 1,344 | 緑内障手術(水晶体再建術併用) | 59 |
| 硝子体手術 | 334 | 緑内障手術インプラント挿入術 | 44 |
| 増殖性硝子体網膜症手術 | 10 | 翼状片手術(弁移植) | 19 |
| 黄斑下手術 | 3 | 後発白内障手術 | 100 |
| 網膜復位術 | 11 | 網膜光凝固術 | 148 |
| 緑内障手術(濾過手術) | 9 | 虹彩光凝固術 | 8 |
| 緑内障手術(流出路再建術) | 12 | 硝子体注射 | 1,211 |
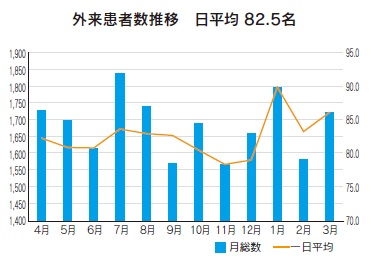
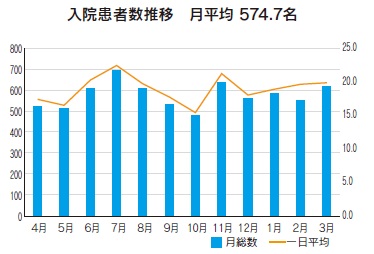
外来のご案内
医師紹介
原 祐子野田 遼太郎
廣畑 俊哉
福本 健
特殊治療について
多焦点眼内レンズ
白内障とは、目の中の『水晶体』が濁り、光がうまく通過できなくなってしまうことです。 手術ではこの濁った水晶体を超音波で砕いて除去し、代わりに人工の眼内レンズを挿入します。
 |
 |
白内障のない見え方 |
白内障の見え方 |
現在使用されている眼内レンズは単焦点レンズといい、ピント合わせをする調節力がないため、ひとつの距離にだけ焦点が合うようになります。ですから、白内障の手術をして、遠くの物も、近くの物も両方くっきり見えるようになるというわけではありません。
眼内レンズの焦点を遠くに合わせた場合、近くの読み書き・パソコン等には眼鏡が必要になります。近くに合わせた場合は運転時等遠くを見るために眼鏡が必要となります。
多焦点眼内レンズでは、1ヶ所だけでなく、遠くにも近くにもピントが合うように設計されています。
手術後に単焦点眼内レンズと比べて見たい所やものの位置に合わせていくつもの眼鏡を使ったり、頻繁に眼鏡をかけはずしたりすることから解放されます。
多焦点眼内レンズはすべての方が適応となるわけではありませんので、詳しいことは医師とご相談ください。
 |
 |
単焦点眼内レンズで 遠方に合わせた場合 |
近方に合わせた場合 |
 |
|
多焦点眼内レンズの見え方 |
|
専門外来について
斜視弱視外来 2022年2月から第2・第4木曜日・午後
弱視について
生まれてすぐの赤ちゃんは明暗がわかる程度ですが、物を正しくしっかり見ることで目や脳が刺激され、6歳ぐらいでほぼ大人と同じくらいの視力に発達します。しかし、器質的(角膜・水晶体や網膜など目自体)に病気がなくても、屈折異常などがあると視力は十分に発達しません。このような状態を弱視といいます。
屈折異常とは、近視・遠視・乱視等によってピントが合わず物が鮮明に見えない状態です。ピントを合わせる為に、眼鏡を使用します。
これによりしっかりと物を見ることが出来、目や脳が刺激され視力が発達します。
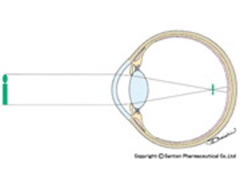 |
|
近 視 |
遠 視 |
屈折異常を調べるために
物を見ようとするときには目の中の筋肉が緊張して、水晶体の厚さを増し、ピントを合わせます。この働きを調節と言います。小児では、この調節力が強く普通の状態で検査をしても正確に屈折検査が出来ません。このため調節麻痺剤を使用し、一時的に調節する力を取ってしまいます。
目を細めていないか、テレビに近づいていないか、顔を傾けて物を見ていないかなど注意してみてください。これらの事に気がついたとき、気になる事があったときは自己判断せず眼科を受診してください。
斜視について
斜視とは、両目の視線が正しく見る目標に向かわないものをいいます。外見上は片方の黒目の位置がずれるもので、内側(鼻側)へずれるものを内斜視、外側(耳側)へずれるものを外斜視といいます。また、上側、下側にずれるものを上下斜視といいます。