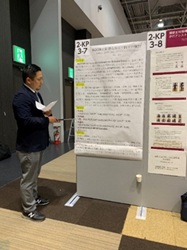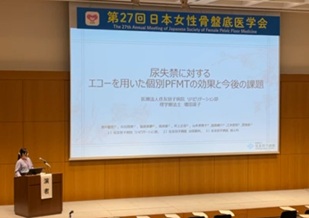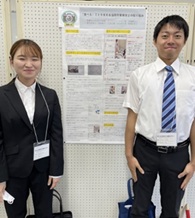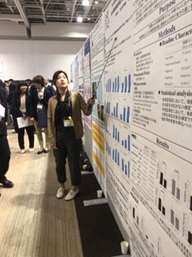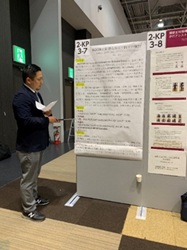研究(新着順)
第27回日本女性骨盤底医学会 ※新着:2025年7月5日~7月6日
第27回日本女性骨盤底医学会がアクロス福岡で開催されました。
昨年度から開始した当院での自費診療外来による骨盤底筋群ケアプログラムに関連して、
当院からは浅井聖史泌尿器科長、篠原実夢・増田遥子理学療法士が公演発表を行いました。
発表内容は、以下のとおりです。
泌尿器科長 浅井聖史

1.住友別子病院 泌尿器科 2.愛媛大学医学部附属病院 形成外科 3.住友別子病院 婦人科
◯浅井聖史1)、
森秀樹2)、
曽我部裕文1)、
宗宮快1)、
山本恵理子3)、
篠森健介1)、
桑野晴美1)
【目的】陰唇癒着症は左右の陰唇同士が癒着する疾患であり、
低エストロゲン状態の関与が考えられている。今回我々は閉経後女性の陰唇癒着症に対して、
排尿障害を改善するために形成術を施行した。
【方法】症例は68歳女性。52歳閉経、
62歳骨盤臓器脱に対して膣式子宮全摘術および前後膣壁形成術施行歴あり。
排尿後尿滴下および外陰部痛が数ヵ月継続するため前医受診し、陰唇癒着症と診断され当科紹介受診となる。
排尿困難および排尿痛があり、排尿機能検査において尿流率低値と残尿がみられた。
外陰部所見は、両側の陰唇は完全に癒合し、ピンホール状の尿出口部は同定できたが外尿道口や膣、
陰核は視認不可であった。骨盤MRIでは、膣疑いはあるも尿道の同定はできなかった。
腰椎麻酔下に陰唇癒着症に対する形成術を施行した。
手順)尿出口部から鈍的および鋭的に上下に切離し、膣、外尿道口、陰核が露出するまで癒着剥離をすすめた。
両側の癒着剥離部の皮膚を切除および縫合し会陰形成した。
【結果】形成術により排尿障害は改善した。患者自身による外陰部視診および軟膏塗布を指導し退院とした。
切除組織に悪性所見はみられなかった。
【考察】陰唇癒着症は、外陰部の視診により診断可能である。女性の排尿障害においては外陰部の診察を考慮すべきである。
陰唇癒着症が高度の場合には形成術も適応となり、その際は再発リスクをふまえ術後フォローアップも必要である。
【結論】陰唇癒着症に対する形成術は機能回復に有効である。
理学療法士 篠原実夢(RASC施行後の尿失禁に対するエコー(M-mode)を用いたStanding PFMTの効果)

1.住友別子病院 リハビリテーション部 2.住友別子病院 泌尿器科 3.住友別子病院 婦人科
◯篠原実夢1)、
浅井聖史2)、
増田遥子1)、
白石理美1)、
森政基1)、
山本恵理子3)、
村上正佳1)、
篠森健介2)、
三木哲郎1)、
菅隆彦1)
【目的】当院では2024年8月から骨盤臓器脱・尿失禁患者に対してエコーを使用した骨盤底筋訓練(以下: PFMT)を開始した。
今回、術前より尿失禁を呈し、ロボット支援下仙骨膣固定術(以下:RASC)を施行した患者に対して術後よりPFMTを実施した結果を報告する。
【方法】対象は68歳女性。他院で2020年に膀胱瘤・子宮脱と診断され、ペッサリーで加療されていたが2024年に性器出血を呈し、
当院泌尿器科紹介受診となる。膀胱瘤StageⅢと診断されRASC施行した。術前より腹圧性尿失禁がみられており、
術後2か月からエコーを用いたPFMTを開始した。立位で畜尿状態の膀胱を経腹的エコーにて描写し、
M-modeにて膀胱底の収縮速度・収縮時間・高さを定量化した。骨盤底筋群(以下:PFM)の収縮感覚を習得してもらい、
PFMT を2か月間、合計9回介入しながら自宅で自主訓練を実施して頂いた。
【結果】Standing PFMT導入前後で収縮速度は0.2cm/sから1.6cm/s、収縮時間は960msから500ms、
高さは0.2cmから0.8cmとなった。ICIQ-SFは7点から4点となり、パッド使用枚数は6枚/日からパッド不要となった。
【考察】患者自身がエコー画面での視覚的フィードバッ クを受けることにより、PFMの収縮が可能となった。
また、立位で尿失禁のある患者に対して、Standing PFMTを導入することで、
日常生活動作に直結したトレーニングとなり有効なPFM収縮が獲得された。
実生活でも立位でのPFM収縮が得られ、最終的に尿失禁の改善がみられたと考える。
【結論】エコーを用いたStandingPFMTは、RASC施行後の患者においても問題なく実施でき、
術後の腹圧性尿失禁の改善に有用であった。
尿失禁が出現する肢位に応じたPFMTを実施することで問題に対して直接的アプローチができ、
尿失禁が改善しQOLの向上に繋がった。
理学療法士 増田遥子(尿失禁に対するエコーを用いた 個別PFMTの効果と今後の展望)
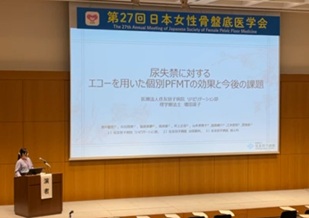
1.住友別子病院 リハビリテーション部 2.住友別子病院 泌尿器科 3.住友別子病院 婦人科
◯増田遥子1)、
浅井聖史2)、
白石理美1)、
篠原実夢1)、
森政基1)、
山本恵理子3)、
村上正佳1)、
篠森健介2)、
三木哲郎1)、
菅隆彦1)
【目的】当院では2024年6月に泌尿器科医・婦人科医・理学療法士による骨盤底専門チームを結成し、
翌年1月より骨盤底機能改善を目的に保険外診療を開始した。
尿失禁に対するエコーを用いた個別骨盤底筋群体操(以下:PFMT)の効果について検討した。
【方法】対象は腹圧性尿失禁を有する4症例と切迫性尿失禁を有する1症例の計5症例。
介入前後での骨盤底機能の変化を比較した。骨盤底機能は経腹的超音波断層法で畜尿状態の膀胱を前額面で描写し、
臥位・立位にて骨盤底筋群(以下:PFM)収縮時の膀胱底挙上による動的変化をM-modeで定量化した。
PFMTや自主訓練指導の際は、視診や触診に加え患者と共にエコー画面を確認しながら実施した。
【結果】平均132日間、10.8回の個別PFMT指導を実施した。
臥位での収縮の高さの平均値は介入前後で0.7cmから1.1cmとなり変化率は+61.7%、
収縮速度は3.8cm/sから4.4cm/sとなり+16.8%であった。
立位での収縮の高さは0.3cmから0.7 cmとなり変化率は+133.3%、収縮速度は1.7cm/sから3.4cm/sとなり+100%であった。
また介入が終了した2症例に実施したICIQ-SFでは平均で8.5点から5.5点に変化、OABSSでは4点から1点への変化を認めた。
1日のパッド使用枚数は3.5枚から2枚へ減少した。
【考察】 全症例において介入前から臥位時の尿失禁症状は認めず、臥位での骨盤底機能は比較的保たれていたと考える。
しかし立位時では介入前から全症例で症状が出現しており、
立位での骨盤底機能が低下した状態であったため変化率が高いと推察した。このことから、
症状の出現場面を考慮したPFMTを指導することが効果的であると考えた。
【結論】尿失禁に対するエコーを用いた個別PFMTは有効であった。今後は症例を重ねていき、
骨盤底機能や代償動作の評価等を再検討し信頼度の向上に繋げていきたい。
またエコーを用いたPFMT時の目標数値の算出や若年層への介入拡大、地域への取り組み等も実施していきたいと考える。
第24回愛媛県作業療法士学会
2024年第24回愛媛県作業療法士学会にて発表し、2名が奨励賞を受賞しました。
2024年8月25日、松前総合文化センターで開催された第24回愛媛県作業療法士学会に参加し、
当院作業療法士3名が一般演題発表とポスター演題発表を行い、その内2演題の奨励賞を受賞しました。
演題『食事動作自立から他のADL自立に繋がった事例~食べやすさに着目して~』では当院作業療法士が入院早期から食事動作のリハビリを積極的に行ったことで、
“おいしく楽しく食べる”ことにつながった症例報告と、演題『「食べる」ことを支える当院作業療法士の取り組み』では作業療法士と言語聴覚士が共同で食事申し送り表を作成、運用し、
病棟での日常生活の支援に繋げた取り組みの紹介を発表しました。
学会発表が初めてで、本番では緊張しましたが、たくさんの意見やアドバイスをいただき、大変勉強になりました。
また、演題『新居浜市地域リハビリテーション活動事業に関わるOTの役割と課題』では、
病院勤務でありながら地域リハビリテーション活動事業に取り組む現状報告を行い、
他市町村で活動している作業療法士との情報交換の機会を得て、有意義な時間を過ごすことができました。
今後は、今まで以上に広い視野を持って、患者さんに効果的なリハビリが提供できるよう努力してまいります。
奨励賞受賞者:池田 裕子・坂東 紀吏子
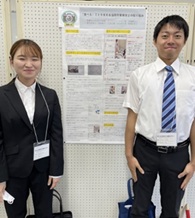
日本リハビリテーション学会・日本理学療法士協会専門部会・日本作業療法士学会
『人工膝関節施行患者の主観的評価と客観的評価との関連』
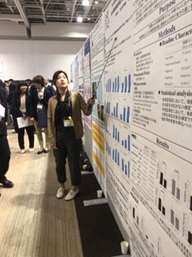
『当院での上肢骨折患者における転倒予防対策の取り組み』